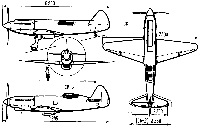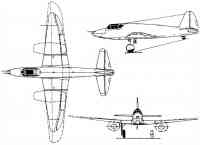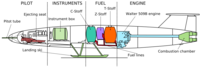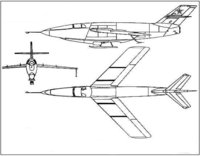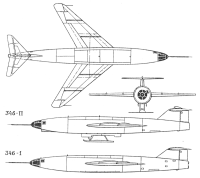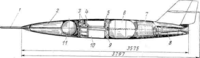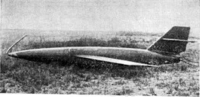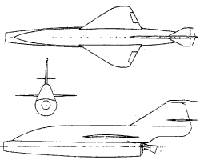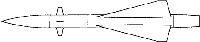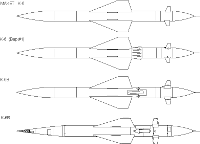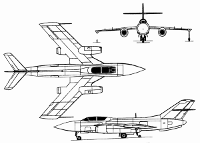1905年にウクライナの都市ニコポリで生まれたマトゥスは絵画に熱中する青年時代を送りました。
芸術教育機関「ヴフテマス」 1-1にも顔を出し、当時の多くの芸術家たちと交流したそうです。
しかしある時航空工学を志し、回り道をしながらも1926年にモスクワ高等技術学校航空・機械学科 1-2に入学しました。
航空技術が急激に発展する中、1930年学科はモスクワ航空大学(MAI) 1-3として独立。
31年に卒業したビスノヴァートは最初期の卒業生の一人です。
MAIは今に至るまで国やメーカーの手厚い支援を受けており、ロシアの航空技術者への登竜門といえます。
1-1 ВХУТЕМАС, Высшие художественно-технические мастерские
1-2 Аэромеханический факультет, Московское высшее техническое училище
1-3 МАИ, Московский авиационный институт